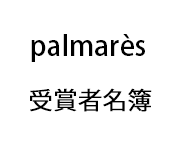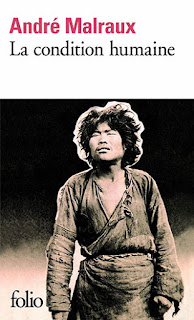Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L’angoisse lui tordait l’estomac ;
- André Malraux, "La Condition humaine", 1934
アンドレ・マルロー (1901-1976)の代表作『人間の条件』(1934)の出だしです。
→
André Malraux, "La Condition humaine" (amazon)
まず最初の文の発音です。
Tchen tenterait-il
チャン タントゥレティル
de lever la moustiquaire ?
ドゥ ルヴェ ラ ムスティケール
Tchen ... ?
チャンは...か?
Tchen は「チャン」で、人の名前でしょう。フランス人の名前じゃなく、東洋人っぽい名前です。
この引用文は小説の冒頭の一文目なので、 Tchen という名前がいきなり出てくると、小説の舞台は東南アジアなのかな、それともこのチャンというアジア人らしき人物が主人公なのかななど、いろいろ思わせられます。
ついで、
Tchen tenterait-il ...?
と続きます。
tenterait は動詞 tenter の直説法半過去形でしょうか、それとも条件法現在形でしょうか?
直説法半過去形と条件法現在形は活用の語尾が似ているので、慣れていないと迷います。
いまそれぞれの活用の活用語尾だけを抜き出してみます。
※ ハイフン(フランス語ではトレデュニオン trait d'uion)は活用語幹を表しています。
○ 直説法半過去
je -ais
tu -ais
il -ait
nous -ions
vous -iez
ils -aient
○ 条件法現在
je -rais
tu -rais
il -rait
nous -rions
vous -riez
ils -raient
じっと見ると分かりますが、条件法現在形の活用は、直説法半過去形の活用語尾の前に r を付ければよいです。
つまり直説法半過去形の活用を覚えれば条件法現在形の活用はらくちんです。
さて、それぞれの活用語尾はわかりましたが、活用語幹はどうなるのでしょうか。
まず、 直説法半過去形の活用語幹は、直説法現在形の一人称複数形、つまり nous に対する活用の語幹と同じになります。
つまり tenter という動詞だと、直説法現在形で nous の場合は、
nous tentons
となりますから、この tentons から最後の -ons を取り去った、
tent-
が tenter の直説法半過去形の活用語幹です。
活用してみましょう。
je tentais (ジュ タンテ)
tu tentais (テュ タンテ)
il tentait (イル タンテ)
nous tentions (ヌゥ タンティオン)
vous tentiez (ヴゥ タンティエ)
ils tentaient (イル タンテ)
話は戻って、そんな面倒なこと言わなくても、動詞の原形(不定詞)から -er を取ったのが直説法半過去形の活用語幹だと言えばいいのでは?
たしかに tenter や aimer など -er で終わる動詞(いわゆる第一群規則活用動詞)はそう言えるかもしれません。
が、たとえば finir だとそうはいきません。
finir の最後の -ir を取り去った fin- は直説法半過去形の活用語幹にはならないのです。
finir の直説法現在形の活用は、
je finis (ジュ フィニ)
tu finis (テュ フィニ)
il finit (イル フィニ)
nous finissons (ヌ フィニソン)
vous finissez (ヴ フィニセ)
ils finissent (イル フィニッス)
となるので、 nous finissons の finissons から最後の -ons を取り除いた、finiss- が直説法半過去形の活用語幹になります。
ですので finir の直説法半過去形の活用は、
je finissais (ジュ フィニセ)
tu finissais (テュ フィニセ)
il finissait (イル フィニセ)
nous finissions (ヌ フィニスィオン)
vous finissiez (ヴ フィニスィエ)
ils finissaient (イル フィニセ)
となります。
(続く)
◇ 翻訳
『人間の条件』の翻訳は新潮文庫から出ていたようですが、今は手に入らないようです。
Amazon.co.jp のマーケットプレイスでは数千円で出てたりします。